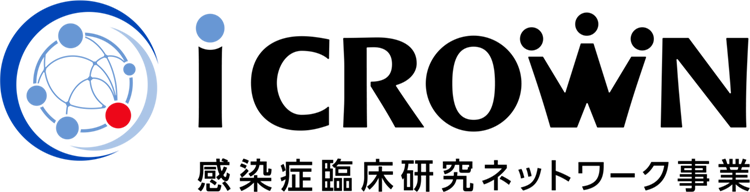利活用手続き
・利用方法
Q1. ショーケースの利用にあたって必要な手続きはありますか。
Q2. 利活用を行うにあたり、eラーニングは誰が受講するべきでしょうか。
研究責任者、また利活用される試料・データによって、試料・病原体・情報のそれぞれの取り扱い責任者に受講をお願いしています。なお、リポジトリポータルのアカウント作成にもeラーニングの受講が必要です。
・利活用条件
Q1. iCROWNのリポジトリの試料・データ の利活用は誰でもできますか。
iCROWNのリポジトリの試料・データは、病院、研究機関、行政、企業など、研究を計画されている研究者であれば、どなたでも利活用の申請が可能です。申請後、利活用小委員会による承認が得られれば利活用可能です。
・スケジュール
Q1. iCROWNのリポジトリの試料・データの利活用申請をしたいと思っています。申請の締め切り日を教えてください。
締め切りはございません。利活用小委員会はおおよそ月に1回程度開催しておりますので、申請いただいた日より一番近い利活用小委員会で審査いたします。詳細はこちらのページの⑤研究相談、⑥利活用申請をご覧ください。
Q2. 利活用申請をしたデータは、申請後に利用可能となるまでどのくらいの時間がかかりますか。
利活用小委員会はおおよそ月に1回程度開催しており、申請いただいた日より一番近い利活用小委員会で審査いたします。承認されましたら、データ準備に1ヵ月程度を要します。そのため、申請からデータの利用開始まで、おおよそ2ヵ月程度かかります。なお、ヒトゲノムデータについては、申請するデータの種類、症例数によってはさらに数週間かかる場合もあります。詳細はこちらのページの「試料及びデータ利活用タイムライン・審査フロー」をご覧ください。
Q3. 利活用申請をした試料は、申請後に利用可能となるまでどのくらいの時間がかかりますか。
利活用小委員会はおおよそ月に1回程度開催しており、申請いただいた日より一番近い利活用小委員会で審査いたします。承認されましたら、試料準備に1ヵ月程度を要します。そのため、申請から試料の利用開始まで、おおよそ2ヵ月以上かかります。詳細はこちらのページの「試料及びデータ利活用タイムライン・審査フロー」をご覧ください。
・申請方法
Q1. ショーケースで気になる試料がありました。どのように申請すればいいですか。
iCROWN利活用窓口に、ショーケースで検索された試料のIDをお教えください。ご相談の上で利活用をご希望される場合には、利活用申請方法をご案内いたします。
Q2. ウイルス分与を希望する場合、変異株が出現する度に、新規で申請書を提出する必要がありますか。
変異株を用いた研究であることを利活用申請書に記載いただき、利活用小委員会で承認される必要がありますが、承認後は、当該申請内容の範囲内で、新規申請書を作成することなく変異株の追加提供が可能です。
Q3. 倫理審査対象外の研究においてiCROWNのリポジトリの試料・データを利活用したい場合は、どのように利活用申請したらよいでしょうか。
利活用申請時に必要な倫理審査に用いた研究計画書と倫理審査委員会承認通知書の代わりに、利活用者の所属機関からの「倫理審査不要の判断書類等」の提出、あるいはiCROWNのリポジトリで用意した「研究倫理審査対象外報告書」の提出をお願いいたします。
・契約手続き
Q1. 利活用の試料等提供基本契約書(MTA)を、複数年度にわたって締結することは可能ですか?
利活用者とのMTAの契約期間は原則、利活用申請書及び研究計画書に記載された研究期間に準じます。期間は最長5年までとしています。但し、年度毎に報告書を提出していただきます。
試料・データの提供方法と条件
・試料の提供
Q1. iCROWNのリポジトリの試料やデータを利活用する場合に、費用の負担はどうなるのでしょうか。
iCROWNのリポジトリで指定している目的に合致している場合は試料・データの利用料は無料です。ただし、試料・データ提供に必要な輸送料等は、実費を利活用者に負担していただきます。また、個人情報保護の観点から、一次データは国立健康危機管理研究機構(東京)に設置されている解析室でのみ解析することができますが、交通費などは自己負担となります。
Q2. 提供される試料について、症例数や量に制限はありますか。
利活用規約では、以下の症例数・量を目安とした利活用が可能であると規定されています。ただし、利活用小委員会にて承認された場合は、記載の目安量を超えて利活用することができます。詳細は公開文書より、利活用規約をご覧ください。
- 症例数の目安:50症例
- 1採取あたりの量の目安:
- 血漿 200 μL
- PBMC 5-50×10^5 cells(保存時のカウント)
- DNA 2μg程度
- 鼻咽頭ぬぐい液 200 μL程度
- 唾液 200 μL程度
- 便 1g程度
Q3. パンフレットに「提供される試料は原則として1回につき50症例以内です。」とありますが、臨床情報およびゲノム情報についても提供する症例数に制限がありますか。
臨床およびゲノム情報の提供数については制限はありません。利活用小委員会にて承認された後は、承認の範囲内で、利活用可能なすべてのデータをご活用いただけます。
また、保管している試料については限りがあるため50症例分を目安としていますが、研究で必要な数量については申請後、利活用小委員会で承認されれば使用可能です。
・臨床情報の提供
Q1. 臨床情報はどのような形で提供されますか。
臨床情報は、研究代表機関である国立健康危機管理研究機構(東京)で設置した解析用端末において解析可能な形(CSV等)で提供します。臨床情報をはじめ、iCROWNのリポジトリで収集されたすべてのデータは、iCROWN事務局のある国立健康危機管理研究機構(東京)の外部に持ち出すことはできません。
Q2. 臨床情報を解析室で利用する前に臨床情報に関するデータ定義書を事前に見ることはできますか。
申し訳ありませんが、試料等提供基本契約書(MTA)の締結前にデータ定義書をお見せすることはできません。利活用申請が承認され、MTAの締結が完了した段階でしたら、データ定義書をお渡しすることが可能です。ご希望の場合は、iCROWN利活用窓口までご相談ください。
・解析室
Q1. 解析をする場所はありますか。
研究代表機関である国立健康危機管理研究機構(東京)の内部にiCROWNのリポジトリの解析室を準備しております。
保管している試料・データ
・全般
Q1. iCROWNのリポジトリにはどのような疾患・試料が保存されていますか。
令和7年4月現在のiCROWNのリポジトリの対象疾患は、重症急性呼吸器感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)、エムポックス、原因不明小児肝炎、入国時ゲノムサーベイランスの試料です。収集保管している試料は、血漿、DNA、PBMC、ぬぐい液、唾液、便、分離病原体等です。
Q2. どの期間の試料・データがありますか。
疾患により異なります。ショーケースで個別症例の概略を確認することができますので、ご希望の情報をご確認ください。なお、ショーケースで更新されてない最新の情報および公開されていない疾患については、iCROWN利活用窓口にご相談ください。
Q3. 試料に付随する臨床情報はありますか。
原則、試料に付随する臨床情報はあります。但し、症例によっては欠測している項目もありますのでご了承ください。
Q4. 試料の提供には、どのようなチューブを使用していますか。
PBMCは1.5mlアゼンタチューブを使用しています。血漿、DNA、鼻咽頭ぬぐい液、唾液、便等は1.0mlアゼンタチューブを使用しています。
・ヒトゲノム情報
Q1. ヒトゲノム情報を取得しているシークエンサーはどこのものですか。
二色蛍光検出の次世代シークエンサー NovaSeq 6000システム(Illumina社)を用いて全ゲノムシークエンスを行っています。
Q2. ライブラリの断片化法を教えてください。
DNA Shearing システム(Covaris社)を用いた超音波法になります。
Q3. シークエンスライブラリのインサート長を教えてください。
基本的には550bpとしておりますが、ごく一部のサンプルでDNA濃度などに問題があったサンプルについては350bpにて断片化しております。
Q4. シークエンスの1検体あたりのデータ取得量はどのくらいですか。
重複リードを除き900億塩基 (90G塩基)以上のデータを取得しております。
Q5. どのようなヒトゲノム情報が利活用できますか。
サンプルごとのgVCFファイル並びに既にジョイントコールされているサンプルについてはVCFファイルが利用できます。また、一部の検体では次世代シークエンサーにより取得したHLA多型情報も利用できます。
Q6. ヒトゲノムデータをマッピングしているゲノムリファレンスのバージョンはいくつですか。
GRCh38/hg38です。
Q7. ヒトゲノムデータに同一検体や家族検体が含まれる可能性はありますか。
iCROWNのリポジトリでは、同じ患者さんが他の施設で新たに登録された場合は、別のIDを附番して管理しておりますので、原理的に同一サンプルのデータが含まれる可能性はあります。また、ご家族の検体が含まれる可能性もあります。
Q8. 全ゲノムシークエンス後のデータにQCは行っていますか。
QCに関わる項目について検討し、Coverageの平均値が25以下のもの、マップされないreadの割合が8E-4を超えるものについては、利活用の対象検体から除いています。
・臨床情報
Q1. iCROWNのリポジトリで収集しているデータは、医療従事者の報告に基づいていますか。それとも、患者の自己報告に基づいていますか。
臨床データは、各医療機関のカルテの情報が元になっており、医師や看護師など、患者の治療や看護に携わった者が報告した情報となります。それらのカルテ情報をレビューし、研究協力者(医師、CRC等)が電子症例報告書(EDC)に入力しています。
Q2. 収集しているデータの詳細が知りたいのですが、症例報告書(CRF)を見せてもらうことはできますか。
申し訳ありませんが、CRFをお見せすることはできません。利活用を検討されている方は、具体的に必要とされている情報についてiCROWN利活用窓口にご相談ください。相談を通して、ご要望に合う情報の有無等について調査をさせていただきます。
Q3. レセプト情報を用いた研究を実施したいのですが、臨床情報のデータにレセプト情報が含まれるとの理解でよいでしょうか。
レセプト情報の利活用については現在準備中です。
Q4. 臨床情報はどのように収集していますか。
iCROWNにおいて履修が必要なeラーニングを受講した各医療機関のスタッフが、カルテレビューを行って電子症例報告書(EDC)に入力を行っております。
Q5. 臨床情報はどのような品質確認を行っていますか。
事前に作成したデータチェックリストを元に、欠損、欠測、未入力、整合性についてデータチェックを行います。疑義事項はクエリを発行して各医療機関にてデータ修正を行っていただき、正常データをロックすることで均一化と信頼性を担保しています。
・試料
Q1. 検体調整の手技や、調整手順について教えてください。
検体調整の手技や手順は、「試料調整手順書」をダウンロードしてご覧ください。なお、国立健康危機管理研究機構とのMTAを締結後でなければ当該試料をご提供できませんのでご注意ください。
Q2. 試料のクオリティコントロールはどのようにされていますか。
iCROWN参加機関において採取された検体は、iCROWN指定の検査会社により回収され一定の温度下で管理されて検査会社のラボに運ばれます。検査会社にて血液は血漿、PBMC、DNAに調製され、iCROWN指定の保存チューブに分注され凍結されます。これらの試料は凍結したまま国立健康危機管理研究機構に納品されます。その後、DNAの一部はヒトゲノム解析に利用されます。鼻咽頭ぬぐい液、唾液、皮膚ぬぐい液、便などの検体も検査会社にて調製されiCROWN指定の保存チューブに分注し、凍結したまま国立健康危機管理研究機構に納品されます。鼻咽頭ぬぐい液、唾液、皮膚ぬぐい液などの試料の一部は、国立感染症研究所にて病原体ゲノム解析および病原体分離に利用されます。iCROWNのリポジトリでは-80℃及び-150℃の自動倉庫で、24時間365日温度の管理などを行い、試料の質を確保し利活用に円滑に対応できるように保管しています。
Q3. 凍結融解は行われていますか。
試料の種類によっては利活用分注時に行う場合があります。
利活用成果
・成果報告
Q1. iCROWNのリポジトリから提供された試料等を用いて、学会発表や論文掲載をする場合には、どのような手続きが必要ですか。
研究成果等を公表する際は、利活用試料等がiCROWNのリポジトリから提供されたことを謝辞およびmethodsにおいて明示すること、その公表資料の写しを速やかにiCROWN利活用窓口へ送付することが利活用規約に規定されています。詳細は公開文書より、利活用規約をご覧ください。
Q2. 謝辞の書き方を教えてください。
以下の文を例として、適宜修正してご使用ください。
例)The data and biospecimen used for this research were provided from the iCROWN (Infectious Disease Clinical Research Network with National Repository) that was commissioned by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan.
その他
Q1. 感染症臨床研究ネットワークにおけるリポジトリ利活用規約第10条1項の但し書き①「統計学的処理等」とは、どのような処理ですか。
登録症例や収集試料・収集情報の概要の把握、事業の実績報告や利活用相談対応等を目的として、平均値等の統計指標の算出、区間推定や時系列データのグラフ化などを行う情報処理を指しています。臨床情報を用いた統計的検定や、予防法・治療法等の有効性や安全性を評価することを目的とした情報処理は含みません。なお、ジェノタイピングデータに対するジョイントコールは、ゲノム解析研究を行う利活用者が使用するためのデータを作成するために適宜実施しますが、他の研究から移譲された試料を用いて得られたジェノタイピングデータについては、移譲元とiCROWNとの合意内容に基づいて対応を行います。
Q2. 試料管理倉庫の見学はできますか。
申し訳ありませんが見学は行っておりません。