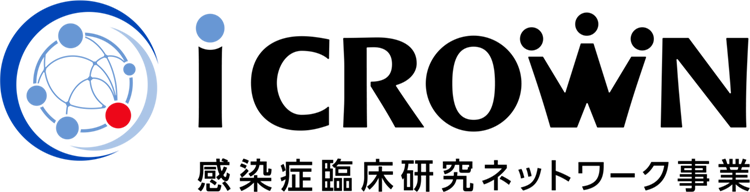・eラーニング
Q1. 研究協力機関では、誰がeラーニングを受講すればよろしいですか。
リポジトリポータルのアカウント保有者全員に、eラーニング受講をお願いしています。具体的には、①iCROWN研究協力責任者(iCROWNに関する施設の責任者)、②生体試料に関する責任者、③生体試料の管理・梱包を行う方、④同意確認・本人確認を行う方、⑤REBIND-IDの発行を行う方、⑥臨床情報をREDCapに入力する方、⑦病院情報システム担当者などが該当します。
Q2. eラーニングに関して、日本学術振興会の研究倫理eラーニングの代わりとして提出可能なものはありますか。
修了日が5年以内のものであれば、ICR-webの臨床研究の基礎知識講座「第9章研究倫理と被験者保護」もしくはeAPRINの医学系研究者標準コース、医学系研究者推奨コース、生命医科学系コース、などでも代用可能です。受講証・修了証のPDFを、リポジトリポータルの所定の場所にアップロードしてください。なお、正式な受講証以外は受け付けていません。
・検体の採取・回収・調整
Q1. 各種検体は、採取後どのように輸送されますか。
検体は、iCROWNが委託している検査会社が施設に回収に伺い、輸送します。すべての検体は採取当日または翌日までに検査会社へ提出してください。
Q2. 土日の検体回収は可能ですか。
検体回収は、月曜日~金曜日のみ行っております。土日、祝日は回収依頼の連絡および回収は受けつけておりません。ただし、営業日前日の休日に採取した場合は、その休日の翌営業日の午前中に連絡がありましたら、基本的にはその日のうちに回収が可能です。iCROWNのリポジトリに参加済みの施設においては、「運用手順書-協力機関用-」の「6.1採取ポイントと検体」、および「7.4検体回収依頼連絡」をご参照ください。
Q3. 検体提出を忘れており、採取から2日を超えてしまいました。この後、検体の取り扱いはどうすればよいでしょうか。
廃棄せずに検査会社にご連絡いただき、提出をお願いいたします。なお、採取当日または翌日に提出できないことが想定される場合は、基本的には検体を採取しないようお願いいたします。
Q4. 余った、または、使用しなかった三重梱包キットや検体採取容器はどうすればよろしいですか。
各施設で廃棄する等、適切に処理してください。
Q5. 入院日と診断日と同意日がすべて異なる場合、どこを採取ポイントの基準日とすればよろしいですか。
同意日にポイント1の検体採取を行った場合は、同意日を基準日にしてください。同意日にポイント1の検体採取ができなかった場合は、ポイント1の採取日を基準日にしてください。例えば、同意日をDay0として、ポイント1をDay1に採取した場合、ポイント2はDay1の3日後のDay4を基準日として採取してください。
Q6. 検体採取はリポジトリポータルに登録された医師だけが可能ですか。
検体採取のみを行うのであれば、登録された医師に限らず、その他の医師、臨床検査技師、看護師などにも採取いただくことが可能です。ただし、採取後の検体管理・梱包等については、実務者の感染リスクを低減させるためにも、リポジトリポータルに登録されたアカウント保有者で、eラーニングを受講後に承認された方のみが実施可能です。
Q7. 対象疾患SARIにおける喀痰検体採取はどのような症例が対象となりますか。
原因病原体が確定していない症例および2類感染症(確定・疑い)症例で喀痰採取をお願いしています。対象症例の選定についてはリポジトリポータルログイン後の関連文書に掲載している各種FAQもご覧ください。
・リポジトリの参加手続き
Q1. iCROWNのリポジトリへの参加にあたって、医療機関ではどのような手続きをすればよいですか。
研究協力機関としてご参加いただく場合、倫理審査は不要です。ただし、研究協力機関として新たに試料・データを収集し、国立健康危機管理研究機構にご提供いただくことになりますので、機関の長への報告・届出、許可書の受領など、「研究協力機関」としての参加手続きをお願いします。
ご提出いただく報告書は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」で公開されている様式に準じたものを作成し、リポジトリポータルのログイン後に公開しています。貴機関で定められた様式がない場合は、ご使用いただき、貴機関で様式が定められている場合は、貴機関指定様式をご使用ください。
Q2. 契約書等の事務手続きはどの段階で行われますか。
リポジトリポータルに施設登録を行いますので、ログインして必要な情報・資料を登録し、申請してください。iCROWN運営支援室にて内容確認後、契約手続きを行います。ただし、契約書のひな型について厚生労働省と国立健康危機管理研究機構とで調整中である場合、直ちに契約手続きが行えない場合があります。
Q3. 症例登録開始は、資材が整えば実施してよろしいですか。
リポジトリポータルにログインしていただき、「関連文書」より運用手順書をダウンロードしてください。運用手順書の「2研究協力機関としての参加登録準備」に書かれている事項がすべて完了していれば、症例登録を開始いただけます。
試料等提供基本契約書は、貴機関で研究協力が許可された日より有効とするような内容で締結いたします。
・試料・データの還元
Q1. iCROWNのリポジトリで収集した自施設の試料・データ等は還元されますか。
症例登録を行った研究協力機関からの申請があれば、自施設の試料・データ(臨床情報・病原体ゲノム情報・ヒトゲノム情報・調製後試料の一部)を還元いたします。還元の頻度は現在検討中ですが、臨床情報は2ヵ月に1回、それ以外はおおよそ年に1回程度です。そのため、迅速な還元は難しいことが見込まれます。
Q2. 自施設で収集しiCROWNのリポジトリに提供した試料の還元を希望する場合の、試料の種類と量を教えてください。
提供いただいた検体量が十分量に達していた場合、原則として採取ポイント1についてDNA・血漿・PBMCを還元いたします。
Q3. 研究協力機関に還元された検体について、他の研究機関に共同研究として検体を提供し、研究に使用することは可能ですか。
iCROWNのリポジトリの研究計画書に基づいて同意を得た範囲において、他研究機関との共同研究として利活用できます。各施設の倫理審査委員会で承認された用途でご使用ください。尚、論文等での公表時には方法・謝辞等に「試料はiCROWNから提供を受けた」旨の記載をお願いします。
・症例登録
Q1. 対象感染症の検査において、長期陽性が確認されている患者でも同意を取得できれば症例登録が可能ですか。
それぞれの疾患の症例報告書(CRF)に記載されている選択除外基準に合致する場合は、登録が可能です。
Q2. 同意説明文書は研究協力機関においてどのように準備すればよいですか。
リポジトリポータルにログイン後、「関連文書」よりダウンロードいただき、印刷して準備してください。なお、研究協力機関名の入力が必要な箇所がございますので、機関名を入力してからご使用ください。運用手順書もダウンロードいただいた上で、手順書の「2.8同意説明用資料の準備」をご確認ください。
Q3. 代諾者による同意取得は可能ですか。
可能です。詳細は、ログインして運用手順書をダウンロードし、「患者登録・同意(IC)取得」の項をご覧ください。
Q4. 一度iCROWNのリポジトリに登録した症例で、再同意を取得しましたが、リポジトリポータルにはどのように入力すればよいですか。
リポジトリポータルにキットIDや同意日・同意書Verを入力する手順は、一の感染症に対して1つのキットIDを使用して1回のみお願いしています。再同意を取得した上で以前登録いただいた時とは異なるキットIDを使用する場合は、リポジトリポータルに新しいキットIDと再同意の同意日・同意書Verを入力し、前回と同じカルテIDを入力した上で再度症例登録を行ってください。
ただし、一の感染症に対して2回以上同意を得た形での再同意を取得し、新しいキットIDを使用しない場合は、リポジトリポータルに登録せずにiCROWN運営支援室にご連絡ください。
Q5. iCROWNのリポジトリにおけるSARI(重症呼吸器感染症)、エムポックス、小児肝炎の疾患定義を教えてください。
・臨床情報の入力
Q1. 電子症例報告書(EDC)においてクエリが発行されるタイミングと、各症例のデータロックが行われるタイミングを教えてください。
クエリは、症例ごとの必須フォームが「確定(Complete)」となったら、症例毎に発行されます。また、各症例において入力が必要なフォームがすべて入力され、ステータスが「確定(Complete)」になり、さらにデータに対する疑義がすべて解消されていればその症例のデータロックが行われます。
Q2. iCROWNでは、電子症例報告書(EDC)はどちらの製品を使っていますか。
REDCapを使用しています。
Q3. 電子症例報告書(EDC)のアカウントの取得方法を教えてください。
EDCのアカウントを取得いただくには、先にリポジトリポータルの利用者アカウントが必要です。医療機関が症例登録を行う施設として登録されている場合、施設内にリポジトリポータルのアカウント管理者がいますので、利用者アカウントの発行をしてもらってください。その際、「EDCを利用する」を選択してください。アカウント発行後、eラーニングを受講して申請いただき、承認されます。承認日の次の月曜日に、EDCアカウントの発行手続きを行っています。
Q4. 電子症例報告書(EDC)に誤って症例を登録してしまった場合、削除方法を教えてください。
施設でお持ちのREDCapアカウントでは、症例を削除することはできません。削除したい症例のPIN番号、REBIND-ID、削除理由や経緯などをiCROWN運営支援室に説明し、削除依頼を行ってください。
・その他
Q1. リポジトリポータルの施設情報に入力したGISAID登録情報は、どのように使用されますか。
ウイルスゲノムの情報をGISAIDに登録する際に、当該検体が採取された機関の情報として使用します。
ウイルスのゲノム解析を行い、解析されたゲノムデータは、国立感染症研究所において、検出された都道府県名と合わせて国際ゲノムデータベースGISAID(Global Initiative on Sharing All Influenza Data)等の公開データベースに登録し、世界中で公開されます。その際、当該ウイルスの元の検体が採取された医療機関名も登録されます。
GISAID登録情報に医療機関名や検体採取関連担当者を入力いただくと貴院の成果とすることもでき、有意義かと思います。医療機関名を公表されたくない、という場合は空欄でも問題ございません。その場合は、検体採取場所は国立感染症研究所として登録されます。
Q2. 事務局がiCROWNのリポジトリの試料・データを用いて学会発表や論文掲載することはありますか。
収集した試料・データの集計結果をまとめて、学会発表や論文掲載する可能性はございます。また、事務局が利活用者として申請し、審査を受けて承認されたのち、試料・データを用いた研究を学会発表や論文掲載する可能性もございます。